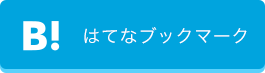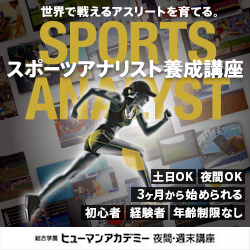【書籍紹介】スポーツはSDGsに貢献できるのか(社会・経済編): 良き在り方(well-being)のためのスポーツを探る
2024年12月24日 書籍紹介 Written by 管理者

著者紹介
小倉乙春(おぐら おとはる)
研究者
研究テーマ:SDGsと地方創生、スポーツビジネス、レジャー、ウエルビーイング、フィットネス
神奈川大学人間科学部特任教授、
早稲田大学スポーツ科学部講師、城西大学現代政策学部講師
2030SDGS、SDGs de地方創生ゲーム公認ファシリテーター、
東京商工会議所健康づくり・スポーツ振興委員会専門委員、
フィットネスビジネス誌にて「欧州フィットネス動向」を連載中(2013年11月号~現在)
主な投稿:「SDG s とスポーツ身体活動産業」「世界ラグビー協会のSDGs活動」「ストリート・フットボール・ワールドの活動」「体育教育の世界的なパラダイムシフト」「ウエルビーイング施策導入国」「公園・緑地の社会価値とロンドン緑地とコロナ復興計画SDGs」「0(ゼロ)次予防医学」、「デジタル治療DTx」など
作品内容紹介
本著ではSDGsが採択される以前から始まっていたスポーツ開発などの事例も含みながら、それらが現在のSDGsへの貢献とどのように関連しているかをまとめることを試みました。スポーツが社会課題解決に貢献できるかどうかについては、本書で伝えていることは、その理念、設計そしてやり方によって貢献の度合いは違い、また、限界もあるということです。一方、スポーツが直接的にあるいは間接的に貢献できる可能性もあることは国連やOECDなど世界的に認められています。
本書の構成は1章ではスポーツ全般への期待、その定義、限界について、2章ではSDGsの歴史的な背景とその意味、3章では世界的なパラダイムシフトを経営、連携モデル、スポーツによる社会課題の取り組みとして記します。4章では日本の現状課題について触れ、5章で直接的にスポーツが貢献できる分野としての教育・健康、街づくり、経済や平等への貢献などについて、そして6章は間接的な貢献として、パートナーシップ、貧困飢餓・産業、つくる責任つかう責任そして気候問題について記しています。そして最後の7章ではスポーツや身体活動などの身近な活動による良き在り方(ウエルビーイング)とSDGsへの関り、さらに活動成果を得るための考え方について紹介しました。
本書は図表を用いた解説を重視し、見開き左に図表を左に開設文章を配した構成になっております。図表解説によるスポーツとSDGsの全体像を大まかにつかんでいただくための概要版でもあります。
是非本著を通してスポーツがツールとして社会問題解決の可能性があることを少しでも皆様が理解し実践できる一助になれば幸いです。
目次
はじめに
1章 スポーツにできること
2章 SDGsとは「誰一人取り残さない
3章 パラダイムシフト
4章 日本の社会課題の現状
5章 スポーツのSDGsへの貢献
6章 スポーツのSDGsへの共創的貢献
7章 身近な活動、成果のためのシステム思考
おわりに
-
【求人情報】〈愛知〉フィットネストレーナー(正社員・業務委託)募集/健康創造企業
【募集職種】フィットネストレーナー「健康創造企業」のプロ集団として、地域住民の健康づくりや企業の健康経営、スポーツ選手におけるトレーニングからアスレティックリハビリテーションまで、幅広く様々な分野の方
-
【求人情報】【インターン】アルバルク東京職業体験型インターンシップメンバー募集
(アルバルク東京 HPより)募集背景アルバルク東京は、まちづくりや社会課題への取り組みに力を入れています今回、一緒にこれらの活動を企画・運営するインターンシップメンバーを募集します。応募資格大学生・
-
【求人情報】東京都世田谷区にある私立学校での部活動指導員募集(剣道)
実施場所:東京都世田谷区にある私立学校[女子校](剣道)実施時期:2026年4月〜2027年3月(継続した活動になります)実施時間:平日及び休日の部活動においての指導(毎週土曜日(14:00-17:0